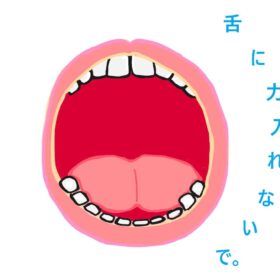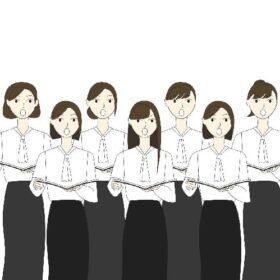昭和の中頃の女性は電話を取る時によく裏声で「ハイもしもし。。」と言う事が有ります。
裏声で薄い綺麗な声は透明感のある女性像とかどんなことでも言う事を聞く良い子とか
あなた色に染まります的な風潮だったんでしょうか。
綺麗な高い声で電話に出ます。
無色透明な声の感じがガメツイ個性は出さないイメージを連想させるのであります。
昭和の美徳なのかもしれませんが。
現代でも、この感じの歌声になってしまう女性が声が通らないと言う悩みを持っています。
現代のポピュラーは現代の社会を生きる人々が作るもの
でその時代のイメージを声が反映しているのかもしれません。
多様性とか自分らしい生き方が、自分らしい声となって流行の歌になるのかもしれません。
現代の歌は自分らしい声で勝負するしかないと思うんです。
それは個性を大事にした自分にしかない個性が詰まった声でメロディーを作り歌となる。
薄い裏声っぽい地声は個性も薄くなって、「キレイな声」ではあるけど
なんとなく現代の歌声にマッチしない感じで聞いていて満足できない感じがします。
歌を聞いて、何が表現したいんだろう?と感じるよりも先に何も感じないと言う事になりがちです。
それでも歌えれば良いと言う人も多いかと思うんですが
聞いている側は、深く考えなくても「何か変かな?」くらいは感じるのかもしれません。
それは現代の社会にマッチしていないからなのかもしれませんね。
特に昔、コーラスをしていたとか声楽をしていたという人は
この事に悩みどうしたら良いか分からないとボイストレーニングを始められる方もいます。
特に昔のコーラスはよく、キレイな声でみんなと合わす事重視で
個性的な声は必要ないという考えでしたかね。
しかし高い綺麗で薄い裏声っぽい地声で全部歌ってしまう事は歌の個性も薄くなってしまい
聞く側に何かが伝わらなくて、少し満足できないので聞いてもらえない歌となってしまいます。
現代の自分らしさと個々を大切にする事とポピュラーミュージックの歌声はリンクしているんだと思います。